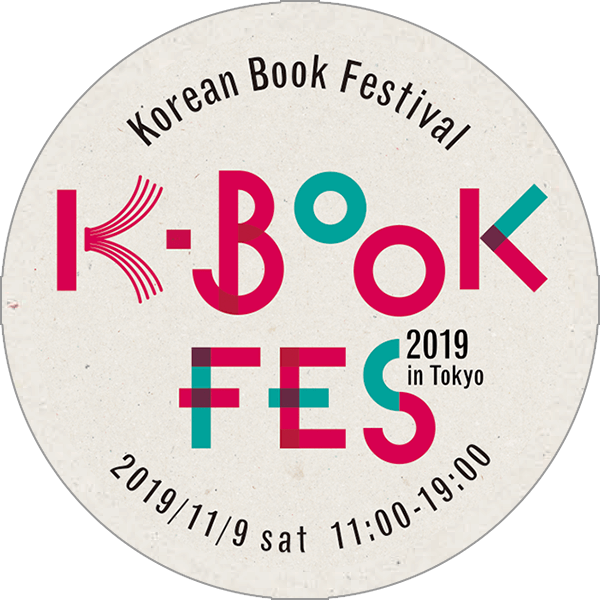『アンニョン、エレナ』
翻訳家・法政大学教授 金原瑞人
去年、『アンニョン、エレナ』を読んで、本当に驚いた。なにより文体が素晴らしい。べたっとした現実感があるかと思えば、ときにユーモラスで、あちこちに思いがけない鮮やかなイメージが錯綜し、はっとするような比喩が飛び交う。
この短編集のなかで、何より鮮烈だったのは「息――悪夢」だ。ここに登場するのは、思いがけない事故で命を落とす母親、それを機に引っ越しをしようとする父親、アメリカに行って帰ってこない双子の兄、そして、主人公だ。人物造形が超人的にうまい。とくに父親。兵役を逃げたあげく、結局、入隊して、むごい目にあい、退役してからは、思考ループのなかにとらわれたままになってしまう。
「ある日、夕食の食材を買って帰ってきた母は、父が水を張った洗面器を食卓にのせ、その中に顔を埋めているのを見た。食卓の上には焼酎の瓶がころがっており、父は全身水をかぶっていた。父が魚になってしまったのだと、母は瞬間的に見てとった」(42頁)
このイメージは見事に母親と父親の人となりと、ふたりの関係を捉えている。そしてこのあと、母親が「ほらほら、鮫のお出ましだよ」というと、父親が洗面器から顔を上げて、「ばかめが。淡水に鮫が住めると思うか?」と怒鳴り、「自分が魚ではないと気づかないわけにはいかなくなった」というくだりは印象的だ。
このあと、母親の殺人未遂、双子の子どもを殺す父親の夢、崖から墜落する母親、「人生でこれからという時になるといつも〈墜落〉〉する父親……などのからめ方もうまい。しかしなにより意表を突くのは、エンディング近くで、真ん中からいきなり飛び出してくる「無」あるいは「喪失」だろう。そしてそのあとににじみ出す、切なさ。ここは解説するわけにはいかないので、ぜひ、読んで確かめてみてほしい。これを読み終えた瞬間、頭のなかに浮かんだのは、マルケスの『百年の孤独』、三島の『天人五衰』、タニス・リーの『タマスターラ』の最初の短編などだ。
『アンニョン、エレナ』には七編の短編が収められているが、父親が海外の港に作った姉妹探しを友人に頼む女性を描いた表題作、地中に埋められた何百年も前の墓誌に憑かれた女性を描いた「チョ・ドンオク、パビアンヌ」、1909年の李完用暗殺未遂事件を扱った「その日」などが文体、構成ともにずば抜けてよくできている。短編小説を読む楽しみにあふれた一冊だと思う。(『ちぇっく CHECK』VOL.1掲載)
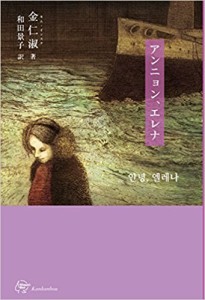
『アンニョン、エレナ』
金仁淑/著 和田景子/訳 書肆侃侃房