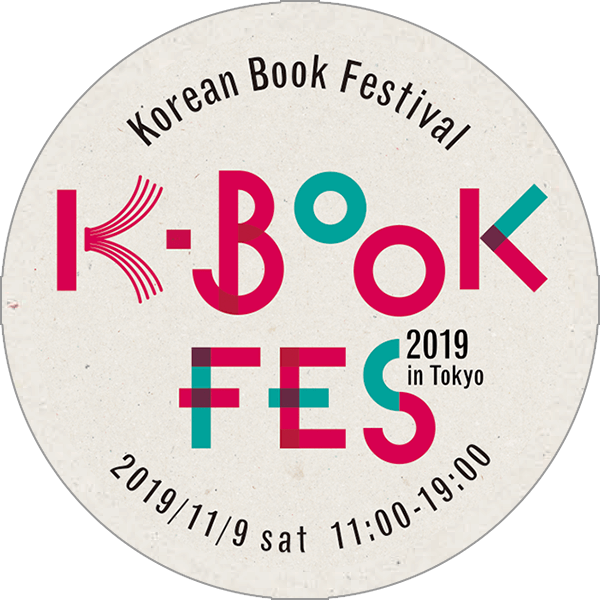【影書房賞】
みのわさん
夢みる「すきま」
 「く、く、口のきけんもんがしゃべった!」。聾唖者に扮して植民地時代を生き延びた共産党の闘士、洪正斗が日本の敗戦を機に語り始めたのを見て、村の人たちは驚く。35年にわたる日本の統治が終わったとき、沈黙していた人々は口々に「夢」を語り出す。『1945、鉄原』は、解放直後に人々が抱いた、その夢を描く小説だ。
「く、く、口のきけんもんがしゃべった!」。聾唖者に扮して植民地時代を生き延びた共産党の闘士、洪正斗が日本の敗戦を機に語り始めたのを見て、村の人たちは驚く。35年にわたる日本の統治が終わったとき、沈黙していた人々は口々に「夢」を語り出す。『1945、鉄原』は、解放直後に人々が抱いた、その夢を描く小説だ。
父親を小作争議で亡くし、地主の家で小間使いとして働く敬愛は、親日派の雇い主が逃げるように去ったのを機に、かつて両親と過ごした小さな家で、2人の姉と平穏に暮らす夢を抱く。根深い男尊女卑が残る旧家の令嬢として生まれた恩恵は、共産党による土地没収により窮地に陥った一族を救うことで、家族に認められようと夢見る。親日派の地主の息子で地元に残った基秀は、幼なじみの敬愛と身分の隔てなく付き合える社会を、奴婢の出の斎英は互いを「トンム(同志)」と呼び合う共産党体制に身分制からの脱出を夢見る。
だが、その夢は潰える運命にある。舞台となる鉄原は38度線に近い街で、かつて南北をつなぐ要衝として栄えたが、現在はその位置ゆえに人が住めない「忘れられた地」となっている。そこは、リアルポリティクスの荒波に多くの夢が押し流された場所なのだ。
主人公の一人である基秀は、解放後に始まった南と北の抗争に巻き込まれ命を落とす。幼なじみの敬愛は彼の死を知り、自分の胸のなかに「すきま」ができるのを感じる。自分が基秀のことをよく知らなかったことに気づいてこう思う。「もう少しよく見ておけばよかったのに。そしたら、すきまに書きこめる話があったはずなのに」。
作者は「あとがき」で現在の鉄原を訪ねた時のことを書いている。リサーチのために鉄原生まれの人を探そうとするが、「だれもがちがうと手をふった」。鉄原で人々が抱いた思いを、証言する人は残っていない。それは、朝鮮半島の精神史に残った「すきま」だ。たが、作者は目をこらして、その夢を幻視しようとする。「1945年の鉄原」は、過酷な現代史の中で朝鮮半島を生きる人々が手放さざるを得なかった夢を復元して書きこむ「余地」として作者に発見されているのだ。
敬愛や基秀の夢は素朴で、私やあなたがかつて抱いた(かもしれない)夢とそう変わらない。ここにあるのは身近な物語だ。「1945年の鉄原」は、隣国を遠くに感じる日本の読者を招き入れるのに十分な幅員を持つ「すきま」でもあったようだ。