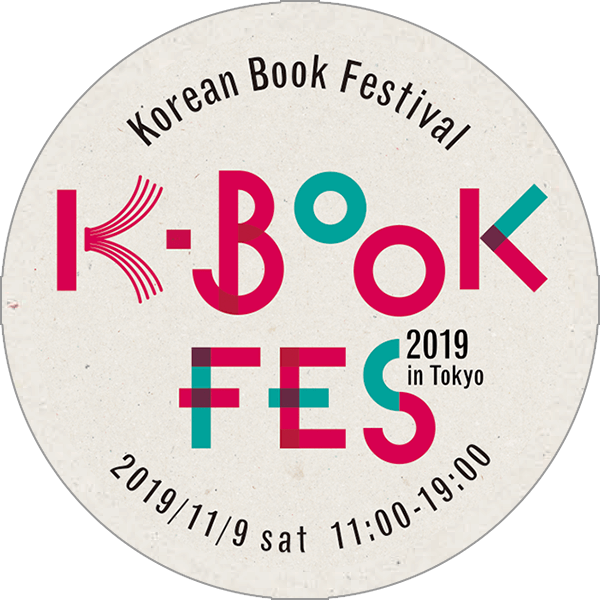『菜食主義者』(韓江著 きむ・ふな訳 クオン)は、「菜食主義者」、「蒙古斑」、「木の花火」という三つの連作中編小説集で す。
す。
「特別な魅力がないのと同じように、特別な短所もない」ヨンヘは、結婚生活5年目のある日突然、怖い夢を見たことから菜食主義者となります。ヨンヘの夫をはじめ、実家の両親など家族は、痩せる一方のヨンヘに対し菜食主義をやめさせようとしますが、肉食を拒み続けるヨンヘは精神に異常をきたし、木になりたがります。
「菜食主義者」は夫の視点から、「蒙古斑」ではヨンヘの姉の夫の視点から、「木の花火」はヨンヘの姉の視点から、狂気に走るヨンヘと周りの家族関係とが描かれていきます。動物と植物の狭間で凄まじく変わりゆくヨンヘの姿に圧倒され、変わりゆく妻についていけない夫の悲しみ、自分も傷ついているのに妹をいたわる姉のつらさに胸が痛くなります。
私はときどき不吉な予感がした。ひょっとしてこれが初期症状にすぎないとすれば?話だけは聞いたことのある偏執病や妄想、神経衰弱などの始まりだとすれば。
しかし、彼女がある狂気に取りつかれているようには見えなかった。彼女はいつものように口数が少なく、家事もきれいにこなしていた。週末には二、三種類のナムルを和え、肉の代わりにキノコを入れたチャプチェを作ったりした。菜食が流行っていることを考慮すれば、不思議なことでもなかった。しかし、彼女が眠れないこと、とりわけ呆然とした顔で何かに打ちひしがれているように見える朝、私がその理由を聞くと、ただ「夢を見たの」と答えるだけだった。それがどんな夢なのか、私は聞かなかった。二度と暗い森の中の納屋、血だまりに映った顔の話など聞きたくなかったのだ。
私が入ったことのない、知るすべもなく知りたくもない夢と苦痛の中で、彼女はやせ続けていった。バレリーナのようにやつれたかと思ったら、ついには病人のようにあばら骨が浮き出るほどやせこけてしまった。不吉な思いがするたびに私は考えた。小都市で材木屋と日用品店を営んでいる義父と義母、人のよさそうな義姉と義弟夫婦を思い浮かべても、精神的な逸脱の血統などとても似合わないと。
彼女の家族を思い浮かべると、立ち込めた煙とニンニクの焼ける匂いが自然と重なった。焼酎を注いだ杯が行き交い、肉の脂が焼けていく間、女たちはキッチンでにぎやかなおしゃべりをした。家族皆が-義父は特に-ユッケが好きで、義母は活魚を刺身にすることができ、義姉と妻は大きな四角い精肉用の包丁を使いこなして鶏一羽をぶつ切りにできる女たちだった。ゴキブリなどは手のひらで打ち殺せる妻の生活力が私は好きだった。彼女は私が選びに選んだ、世の中で最も平凡な女ではないか。
たとえ彼女の状態が心底疑わしかったとしても、いわゆる専門家による相談や治療などについては考えたくなかった。“そんなことはひとつの疾患で、欠点ではない”とこれまで話してきたとしても、それはあくまで他人事に限ってのことだった。私にはまったく、異様なことに対する耐性がなかった。(29頁から31頁)