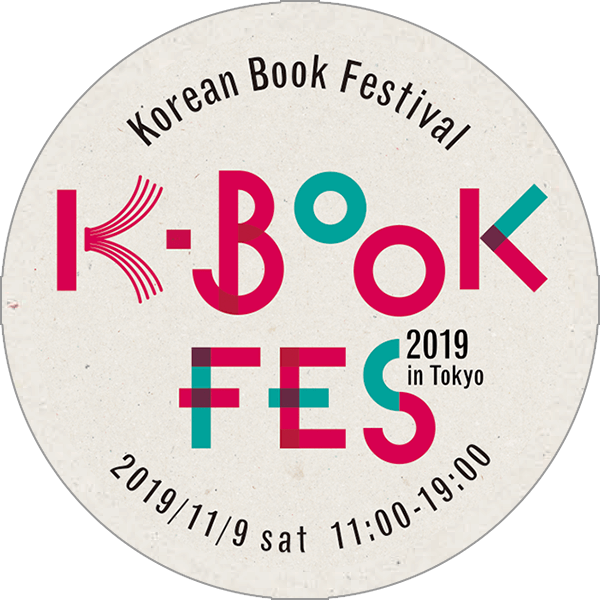日本に生きる私たちに問いかけるもの
作家 姜信子
物語は、拷問技術者である父、安(アン)の独白からはじまる。そして、次に、世間知らずのあまりに無邪気な娘ソニの声がそれにつづく。父は逃亡者の身の上。娘は大学生になったばかり。軽快なテンポで、リズミカルに、時に凄惨な拷問シーンや大胆な性的描写も織り込んで、極限状況に追い込まれてゆく父と、その状況に巻き込まれてゆく娘の独白が交互に綴られてゆく。その独白の声は次第に父と娘の関係性のねじれを浮かび上がらせ、ついには娘による精神的な「父殺し」の様相も帯びてくる……。
日本の読者のなかには、これを荒唐無稽なお話と受け取る向きもあろう。しかし、韓国社会に生きる者にとっては、おそらく、この小説『生姜(センガン)』は圧倒的にリアルだ。なぜならば、ここには、韓国社会が今も抱える深く大きな傷がありありと刻み込まれているから。「父」の時代の深い傷を受けとめよう乗り越えようともがき苦しむ「子」がそこにはいる。
繰り返しよみがえる父たちの亡霊を前に、キャンドルを手に静かな闘いを繰り広げる現在の韓国の市民の姿を想いつつ、この『生姜(センガン)』を味わうならば、葛藤の苦み、それでも消えぬ希望の香りが胸中に広がるようでもある。
さて、ここで、本書を味わううえで極めて重要な歴史的社会的背景を見てみようか。
一九八〇年代、軍事政権下の韓国に拷問技術者と呼ばれた男がいた。李根安(イ・グンアン)。通称「葬儀屋の次男」。この男は、対共分室という「アカ」一掃のための拷問室で、本人曰く「芸術的」な「強制尋問」を執り行った。
李根安によるものではないが、ある学生の拷問死をひとつの導火線に、全国民的な民主化闘争が展開されたのが一九八七年のこと。この民主化闘争で勝利するまで、韓国はいわば、権力による「拷問の時代」にあったとも言えるだろう。(それは日本による植民統治の時代から継承されてきた支配の手段の一つ、ということも日本の読者は忘れてはなるまい)。
拷問の時代、あるいは、力ずくの「支配と服従」の時代を生き抜いた社会に刻み込まれた深い傷。そのひとつの象徴である拷問技術者李根安。一九八八年、その顔が新聞に公表された。李は自宅である美容院の隠し部屋に一一年間潜伏した末に自首し、七年間服役した。そして今なお、李は「愛国」のための拷問を肯定する。
韓国人ならば誰もが知るこの男に、もし娘がいたなら? その仮定を出発点にまさに「娘」世代の作家千雲寧が紡ぎ出した物語は、日本に生きる政治的にあまりに無邪気な私たちにも多くのことを問いかけるだろう。(『ちぇっく CHECK』VOL.1掲載)
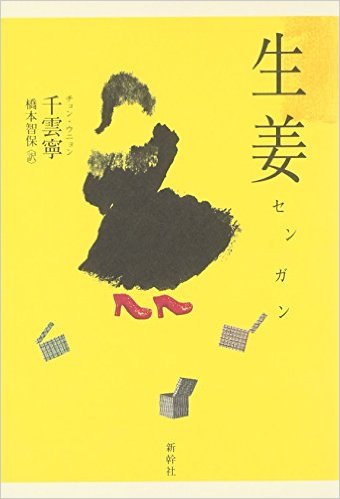 『生姜(せんがん)』
『生姜(せんがん)』
千雲寧(チョン・ウニョン)/ 著 橋本智保/ 訳 新幹社